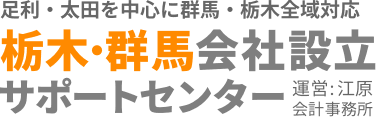

2023年10月1日からインポイス制度がスタートしました。 免税事業者から課税事業者になると、これまでの所得税や法人税の確定申告に加えて、消費税の確定申告も行う必要が出てきます。 新たに課税事業者となった際に必要な、確定申告の基礎知識を説明します。 確定申告の基礎知識 インポイスの請求書ではなくても 1万円未満は仕入税額控除がOK 免税事業者が適格請求...
『倒産』とは法的に定義されている言葉ではなく、会社が資金繰りに窮して、事業を継続できない 状態を指します。 もし、取引先が倒産してしまったら、取引先から債権を回収しなければなりません。 納品済み商品の引き上げのための 所有権留保特約を付帯させておく 一般的に、倒産した企業から債権を回収するのは 非常にむずかしいとされています。 倒産は、経営がうまくいかずに資金不足に陥っ...
作成日:2023年9月10日 大手飲食チェーンでの客による迷惑行為が頻発し、その動画が拡散されて大きなニュースになりました。 これらの迷惑行為を防止するのは簡単ではありませんが、経営の根幹を揺るがしかねないこの問題に、企業としてどう向き合うべきかを考察していきます。 さまざまな業界に広がる迷惑行為、有効な対策を見出すためには? 2023 ...
作成日:2023年7月20日 被相続人が誰かに貸したお金は、遺産の一部として相続税の対象となります。 被相続人が代表取締役社長であり、社長が企業に資金を貸した場合も同様です。 貸付金が高額の場合、相続人の税負担が大きくなるため、事前にできる相続税対策を知っておきましょう。 債権放棄で相続税は課税なし!債務免除益は繰越欠損金で相殺を 中小企業...
作成日:2023年7月10日 経営者や経理担当者の頭を悩ませる問題の一つに、 “使ったお金が経費にあたるのかどうか” の判断があげられます。 これを間違うと、ペナルティが課せられることもあるため注意が必要です。 今回は、経費の基本を改めて確認していきましょう。 国税庁が定める損金に算入できる...
作成日:2023年6月4日 インボイス制度とは 令和5年10月1日より、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。 インボイスとは「適格請求書」のことをいい、売り手が買い手に対して、その取引で適用されている正確な税率や消費税額を伝えるために発行するものです。 インボイスの発行業者は、買い手である取引相手から交付を求められたときは、一定の事項...
2023年10月から「インボイス制度」が開始されます。 この制度の目的は、各種取引の正確な消費税額と消費税率を把握することです。 新制度では、仕入税額控除を受けるには仕入先などが八呼応する「インボイス(適格請求書)」が必要になります。 下記にインボイス制度のポイントと、小規模事業者が検討すべき事項などを解説します。 インボイスを発行できない事業者は取引先減少のリ...
2022年10月から、従業員が101人以上の企業は、 パートやアルバイトなどの短時間労働者であっても社会保険に加入することが義務化されました。 この加入義務の適用範囲は、今後さらに拡大する予定です。 対象となる企業や対応手順を再確認していきましょう。 【対象企業】特定適用事業所とは? 社会保険とは、厚生年金保険や健康保険などのことをいいます。 201...
最近、電子帳簿保存法についてよく耳にすることがあるかと思います。 インボイス制度と併せてよく聞くこの法改正、実際のところ「何を・いつまでにすればいいの?」とお悩みの方も多い方お思います。 本日は制度概要とその対応についてお伝えいたします。 いまさら聞けない・・電子帳簿保存法とは? まず第一に、電子帳簿保存法で定義されていることを細かく見ていきましょう。 電子帳...
最近、インボイス制度についてよく耳にすることがあるかと思います。 2023年10月に施行されるインボイス制度のポイントを再度抑えて、自社の対応を適切に済ませておきましょう。 いまさら聞けない・・インボイス制度って? インボイス制度とは、2023年10月1日から始まる消費税に関する新しい税制のことです。 簡単に言えば、 買手は売手から受け取る請求書が、「インボイ...